��J��w�E��J��w�Z����w���ɂ�������I������̊Ǘ��E�č��̃K�C�h���C��
�@��J��w�ł́A�{�K�C�h���C���Ɋ�Â����I������̊Ǘ��E�č����K���Ɏ��s�����悤�w�߂܂��B
1.�@ ���I������̊Ǘ��E�č��̐ӔC�̐�
�@�{�w�ł́A�w����擪�ɁA�ȉ��̂悤�ȊǗ��E�č��̐ӔC�̐����Ƃ�܂��B
(1) �ō��Ǘ��ӔC�ҁF�w��
�@�{�w�ɂ����錤��������̕s���s�ׂ̖h�~���Ɋւ��ẮA�w������������B
�A�w���́A���������̕s���s�זh�~�̂��߂ɁA�\�����ւ̌[�֊����ɓw�߂�B
(2) �����Ǘ��ӔC�ҁF�w�āE�����ǒ�
�@�����I�������̉^�c�E�Ǘ��ɂ��ẮA�w�āE�����ǒ�����������B
�A�w�āE�����ǒ��́A�����I�����̓K���Ȏ��s�y�щ�v�Ǘ��ɂ��ĐӔC���B
(3) ���ǐӔC��
�@�����I�������̓���I�ȉ^�c�E�Ǘ��̐ӔC�҂�u���A���猤���x�����������������Ă�B
�A���猤���x�������������́A�����I�������̊Ǘ��^�c�Ɋւ���K���Ȏ����葱���̐����ɓw�߂�ƂƂ��ɁA���������x���A�o�[�A�������̎����Ǘ��ɓ�����B
(4) �S������
�@�����I�������ɂ�錤�������x���́A���猤���x�������猤���x���ۂ���������B
�A���猤���x�������猤���x���ۂ́A�����I�������ɂ�錤�������A���������葱���A�����I�������̎g�p�Ɋւ��郋�[���Ɋւ���@�֓��O����̑��k��t�����ƂȂ�B
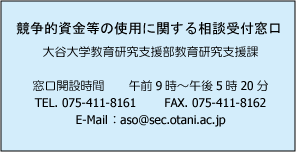
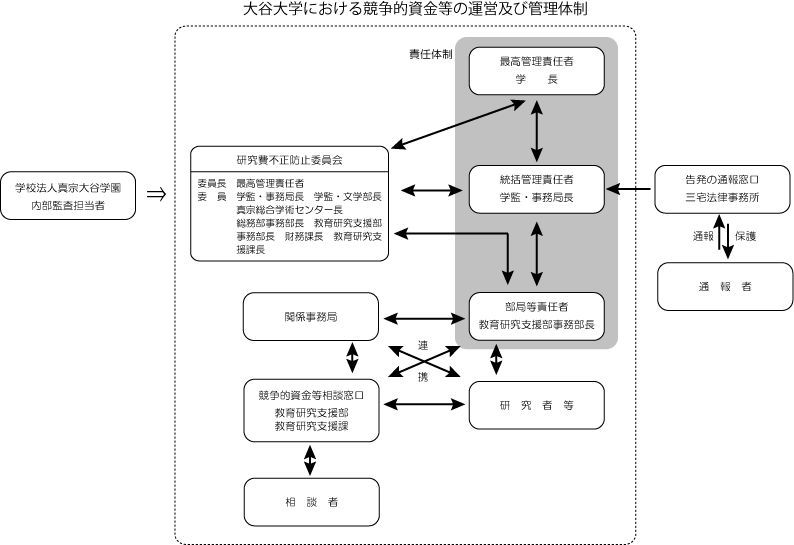
2. �s���h�~�̂��߂̑g�D�̐�
�@�s���h�~�̂��߂̑g�D�̐��́A�h�~�v�搄�i�����ɑΉ�������̂Ƃ��āA�w�����ψ����Ƃ���u������s���h�~�ψ���v��ݒu���A�w�Z�@�l�^�@��J�w���̓����č����x�����p����ƂƂ��ɁA�w�O�ٌ̕�m�������Ɂu�s���\�����đ����v��݂��邱�Ƃɂ��A���I������ɂ�錤���������K���ɐ��i���������ɓw�߂Ă����܂��B
�s�s���s�א\�����đ����t
�@�s���s�א\�����đ����́C�\���ҋy�я��҂̐l���C�l���ی삷�邽�߈ȉ��ٌ̕�m�������ɂ����Ă��܂��B�s���s�א\�����đ����ł́C�s���s�ׂɌW��\�����āA���ꂽ���̐������s���A�����Ǘ��ӔC�҂ւ̎掟�����s���B�����Ǘ��ӔC�҂Ɏ�莟���ꂽ�\�����ē��ɂ��ẮA�ō��Ǘ��ӔC�҂ɑ��₩�ɕ����̐������Ă��܂��B
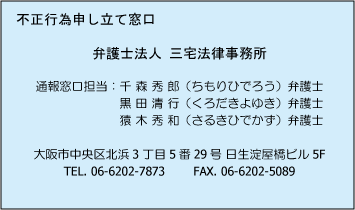
3. �s���Ȏ���Ɋ֗^�����Ǝ҂ւ̏������j
�@�s���Ȏ���Ɋ֗^�����Ǝ҂ւ̏����́A�ȉ��̎��������Ă��A�w�������肷�邱�ƂƂ��Ă��܂��B
(1) �Ǝ҂��傽�铖���҂Ƃ��ĈӐ}�I�Ɍ�����̕s���g�p���哱�����ꍇ�̑[�u
�Ǝ҂������҂Ɏ��������čs���錤����̕s���g�p�A�����ݔ����̋������D�ɂ����čs������D�W�Q���͒k�����A�Ǝ҂��傽�铖���҂Ƃ��ĈӐ}�I�Ɍ�����̕s���g�p���哱�������������������ꍇ�ɂ́A�s���Ɏx�o���ꂽ���Y������̕Ԋ҂����߂�ƂƂ��ɁA�s��ꂽ���ۂ̒��x�A�g�D�Ƃ��Ă̊֗^�̓x���������Ă��A1�N�ȏ�̎����~�����Ƃ���B�������A�����̎����~���{�w�̋��猤�������ɒ������e��������ꍇ�ɂ́A�����Ԃ��o����ɁA�����~�����Ƃ��邱�Ƃ��ł���B
(2) �{�w�̌����҂��傽�铖���҂Ƃ��ĈӐ}�I�Ɍ�����̕s���g�p���哱���A�Ǝ҂��]���铖���҂ł���ꍇ�̑[�u
�����҂��Ǝ҂ɔ����̌��Ԃ�ɔ����t��v������ȂǁA�����҂��傽�铖���҂Ƃ��ĈӐ}�I�Ɍ�����̕s���g�p���哱���A�Ǝ҂�����ɉ��S�������̎��������������ꍇ�ɂ́A�s���Ɏx�o���ꂽ���Y������̕Ԋ҂����߂�ƂƂ��ɁA���̓��e�ɉ����A1�N�ȉ��̎����~�����Ƃ���B�������A�����̎����~���{�w�̋��猤�������ɒ������e��������ꍇ�ɂ́A�����Ԃ��o����ɁA�����~�����Ƃ��邱�Ƃ��ł���B
(3) �s���Ȏ���Ɋ֗^�����Ǝ҂ɂ��ʕ������ꍇ�̑[�u
���k�����ւ̒ʕA�s���Ɋ֗^����������(�Ǝ�)������I�ɖ����o�A�����ɋ��͂����ꍇ�ɂ����ẮA���̓��e�����Ă��������e�����肷��ꍇ������B
(4) ���̑�
�����ҁA�Ǝ҂����d���A�傽�铖���҂̔F�肪����ȏꍇ�ɂ́A���҂��傽�铖���҂Ƃ݂Ȃ����̂Ƃ���B
4. �����E�����Ɩ�
�@�{�w�ł́A���I������ɂ�锭���E�����ɂ��āA���̂悤�Ɏ�舵���Ă��܂��B
(1) �w���E����
�s���ϕ��@�t
�w���́A��w�i�����ҁj���������ɂ��A�[�i���s�U���ɂ�錈�ς������Ƃ��܂��B
�s�����t
�����͌����҂������Ȃ����A�����ɂ��炩���ߔF�߂�ꂽ�ꍇ�������A���O�Ɏ����ǁi���猤���x���ہj�Ƌ��c�̏�A������������̂Ƃ���B���O���c�̂Ȃ������̏ꍇ�A���ς���Ȃ��ꍇ������B
�����ǂ́A�����ړI�Ƃ̐������ɂ��ċ^�`������ꍇ�A�^�@�����w�p�Z���^�[���Ɏ���A���̑Ó����f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�s�^�p���t
��20,000�~�ȉ��̏��Օi�̍w���ɂ��ẮA��w�������ɂ��x�������s�\�ȏꍇ�i���z�A�������ό��蓙�j�ɂ́A�����҂ɂ�闧�֍w����F�߂�B
���Ï��w���Ȃǂ̎��u�����s�\�ȏꍇ�ɂ��ẮA�����҂ɂ�闧�֍w����F�߂�B
���������s�擙�A�����ǂւ̑��k���ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����҂ɂ�闧�֍w����F�߂�B���̏ꍇ�ł����Ă��A�����ړI�Ƃ̐������Ɍ�����Ƃ��ɂ́A���I�������̎x�o���s��Ȃ��B
(2) ����
���ׂĂ̍w�����i�ɂ��Ĕ[�i������猤���x���ۂƂ��A�����ǂ��������s���B
�����͈ȉ��̎����ǂ��S������B
�p�i�E���i�F�����������ێ{�݃`�[���ˎ��Y�o�^���x���\�t
�}���i�o�^���j�F���猤���x�����}���E�����ىہː}�����x���̓\�t
���Օi�y�я�L�ȊO�̕��i�F���猤���x�������猤���x���ہˌ�����
�������҂́A���֍w���������ꍇ�ɂ́A�����ɏߏ��ނ�Y���ċ��猤���x���ۂɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���ʂȕK�v������ꍇ�A���猤���x���ۂ͌������ɏo�����A�����������Ȃ��B
���������s�̒��������̊m�F�͓��挔�̔����ɂčs���B��H�𗘗p���Ȃ��ꍇ�́A���s��ł̊������ؖ����鏑�ނɂčs���B�����҂́A���s�シ�݂₩�ɒ��������쐬���A�����Lj��ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���A���o�C�g���̏o�Ίm�F�́A���猤���x���ۂɔ����t���̏o�Ε�ōs���B�A���o�C�g���́A���炩���ߓo�^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�A���o�C�g���́A���猤���x���ۂɏo���o�Ε�ɓ��ƂƂ��ɁA�o�ދ̎������L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������\�҂͏o�ދ̓��e���m�F�̏�A���猤���x���ۂɐ\������B
5. ���̑�
�{�K�C�h���C���ɒ�߂̂Ȃ��������������ꍇ�ɂ́C�u�����@�ւɂ�������I������̊Ǘ��E�č��̃K�C�h���C���i���{��j�v�i����19�N2��15�������Ȋw��b����j�y�т��̑��̊W�@�ߒʒm���ɒ�߂�Ƃ���A�܂��͂��̎�|�ɏ����Ď�舵�����̂Ƃ���B